こんにちは。
先日、富士吉田市に用事があり
初めて山梨側から富士山を拝みました。


〈人生初の山梨側から見る富士山〉
思いがけず紅葉も楽しめました。




当日が41歳の誕生日だったので
素晴らしいギフトでした。
その後、パートナーが前から
行きたかったというお宿での
養生断食リトリートに参加してきました。
そこで講師をされている方のお一人が
僕のYouTubeやDVDをご視聴されていた
とのことで
「川津先生ですよね」
と声をかけて下さって嬉しかったです。

〈対馬の滝〉
伊豆高原での3泊4日だったのですが
景色も環境も心地よかったので
こちらもYouTubeでシェアしますね。

〈伊豆大島から昇る日の出〉
話は変わって
最近、このブログのシリーズが
影響してるかわかりませんが
台湾で陳式太極拳について研究している
方からメッセージをいただきました。
本人は練習者ではないようですが
当ストーリーに登場する楊益臣先師と
同じように劉慕三のもとで呉式を学び
後に陳発科から陳式太極拳を学んだ方で
その後、台湾へ渡った弟子について
情報を送ってくれました。
台湾ではYouTubeを
「油管」って表現するんですね。
油の発音はYou(ヨウ)
Tube(チューブ)は管なので
そのままっちゃそのままですが
音訳と意訳を混ぜられると
瞬時に推測しにくいです…。
大陸ではGoogleさんがかなり昔に
撤退したので使われてない単語かも
しれないですね。
それでは今回もシリーズの中身に
入っていこうと思います。
初めて当ブログにたどり着いた方は
もちろんのこと
人名を見て「誰だっけ?」って
なりそうな方は以下を読み直してから
今回の内容をご覧ください。
2021年、ある投稿の発見
〈序章1〉
https://shienonekonessblog.wordpress.com/2021/09/28/chen-style-taichi-story1/
2006年、西安での出会い
〈序章2〉
https://shienonekonessblog.wordpress.com/2021/10/11/chen-style-taichi-story2/
2008年、先師の弟のお話
〈第一話〉
https://shienonekonessblog.wordpress.com/2021/10/27/chen-style-taichi-story3/
1928年北京
陳式太極拳を初めて目にした者たちの戸惑い
〈第二話〉
https://shienonekonessblog.wordpress.com/2021/11/07/chen-style-taichi-story4/
__________________
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
シリーズ第5段
『先師の物語』〜第三話〜
推手、陳発科vs劉慕三の結果は!?
__________________
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
ここでお話の続きに入る前に
太極拳に関わる歴史に触れたことの
ない方に起こりがちな疑問に
お答えしておこうと思う。
前話にも系譜で名前が登場している
楊式太極拳の創始者、楊露禅(福魁)の姓と
この物語で
私が先師と呼ばせていただいている
西安で陳式太極拳を伝えた
楊益臣の姓が同じなので
子孫だったり
何か関係性はあるの?
という疑問である。
全ての人は遡っていけばどこかで
共通の先祖に辿り着くという
理屈は抜きにして
祖籍が河北省永年県閻門寨人と
されている楊露禅との間には
血族関係はどう考えてもないだろう。
それは、楊益臣先師の弟、楊徳厚氏の
お話にもあるように彼の一族は
満州民族(女真族)であり
姓も揚古利(1572年-1637年)という
先祖の名前の一文字「揚」の音を
漢民族の姓「楊」に当てて
つけたものだからである。
日本の教科書で清の初代皇帝は
太祖ヌルハチと学んだが
(中国語では”努尓哈赤”と表記)
同じようにその娘婿である”揚古利”という
人名も、もし日本の教科書に載るなら
「揚古利(ようこり)」ではなく
「ヤングリ」とカタカナ表記される
可能性が高い。
(※後日、実際に「ヤングリ」と表記された
日本語の論文を見つけた。)
同じように漢民族の姓をつけた
満州人の中に前話でも登場した
全佑の子、呉鑑泉もいる。
「烏佳哈拉」という満州族の姓の
頭文字「烏」の音と「呉」の音がともに
wu(ウー)なのでそこから
漢民族の姓「呉」をとっている。
烏龍茶(ウーロン茶)の「烏」(ウー)
なので中国語に興味がない方でも
発音には馴染みがあると思う。
楊露禅から学んだ満州族の全佑も
系譜の中では呉式太極拳の初代として
全佑とのみ書かれていることが多いが
たまに呉全佑との表記も見られる。
全佑は1902年、つまり清代に
亡くなっているのでご在命当時は
漢民族の姓は使っていなかったのでは
ないかと推測している。
冒頭の余談が長くなったが
以上、
先祖の名前の一字から音をとって
揚古利→「楊」
満州族の姓の頭文字の音をとって
烏佳哈拉→「呉」
という満州族の人々が発音から
漢民族の姓をつけた事例を紹介
してみた。
_______
前話からの続き
・・・・・・
先師の弟、楊徳厚氏は
話を続けた。
『最初に陳発科より陳式太極拳を学び
始めた電報局の十数人のうち
覚えているのは
劉慕三、楊益臣、李鶴年、劉亮、趙仲民
羅邁敖などだ。
あの頃に学んだのは”大架子”(「大架式」)
といい現在の架式と少し異なっていた。
とても簡潔で、三換掌、退歩圧肘、中盤など
いくつかの動作がなかった。
兄の話によると
劉慕三氏は一路を学び終えた後
単独で陳発科に推手の教えを請いに
行ったという。
兄たちはみな
20年以上呉式太極拳を練っていて
北京の武術界でも名の知れた劉慕三なら
陳発科と推手をしても大差がないに違いない
そう思っていた。
しかし
一手交えてみるとみなの想像とは違い
劉慕三の歩法はふらふらと大いに乱れて
3歳の子どもが大人に弄ばれている
ようだった。
しかも関節の靭帯を挫傷することになり
長い間痛みがとれなかった。
陳発科は後になってこう語った。
「ちょっと軽率だった。
劉さんは勁力があるので
手元が狂ってしまった。」
この一件から誰も陳発科に
推手の教えを請おうとはしなくなった。
陳発科は笑いながら言った。
「緩めて円を描けば受け流せる。
みな私とやってみたらいい。
ちょっと気をつければ何もケガを
するようなことはない。」
・・・
最初のうちは陳発科は
新華門のお向かいの栓馬樁胡同にある
劉慕三の家に毎週1〜2回来て教えた。
通常、兄は毎朝中州会館に行って
陳発科老師に学んだ。
電報局の人たち以外にもこれより以前に
陳発科から学んでいた者が
劉子成、劉子元など他にも数人いたが
みな商売で忙しくしていて
熱心な者はあまりいなかった。』
取材していた李速騰氏は
話を遮って楊徳厚に質問した。
『洪鈞生先生は当時一緒に学んで
いなかったんですか?』
・・・
_________
話の中で兄と表現されている
楊益臣先師の目立つ描写は
今回特になかったが
週に数回学んでいた電報局の
他の人たちと違い
先師が陳発科のもとに毎日指導を
受けに通っていたことがわかって
なんだか嬉しかった。
次回はお話の続きに入る前に
劉慕三に対し私が敬意を持った点
について少し語っておきたいと思う。
〜つづく〜
____________
【お知らせ】
※すでに終了しているイベントが掲載されて
いる場合は、次回の更新をお待ちください。
『しえんプログラム2020』
https://shienonekonessblog.wordpress.com/shien-program2020sales-letter/
【大阪週末クラス最新情報】
https://shienonekonessblog.wordpress.com/osaka-shumatsu-class-news/
【東京ワークショップ最新情報】
https://shienonekonessblog.wordpress.com/tokyo-ws-news/
【鹿児島セミナー最新情報】
https://shienonekonessblog.wordpress.com/kagoshima-seminar-news/
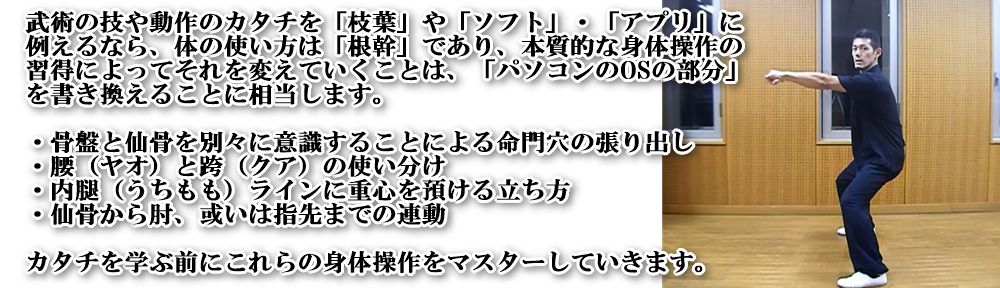
ピンバック: 『先師の物語』〜第四話〜系譜に名を遺していない偉人たち | 中国民間武術研鑽サークル(大阪・東京)
ピンバック: 『先師の物語』〜第五話〜楊益臣先師を敬服していた師兄弟 | 中国民間武術研鑽サークル(大阪・東京)
ピンバック: 『先師の物語』〜第六話〜陳発科による毎朝のマンツーマン指導 | 中国民間武術研鑽サークル(大阪・東京)
ピンバック: 『先師の物語』〜第七話〜西安への移住とその後 | 中国民間武術研鑽サークル(大阪・東京)