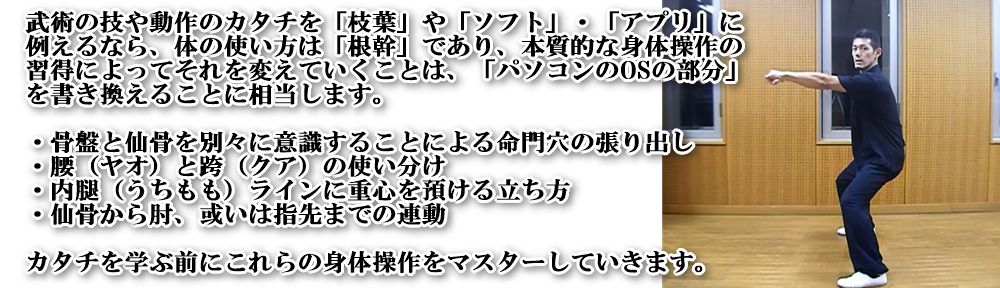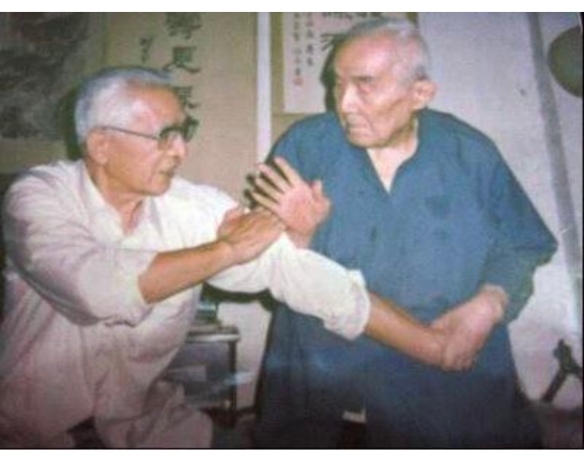こんばんは。
久しぶりの投稿です。
5月上旬、鹿児島へ向かう移動中に
書いています。

いつも初めて飛行機に乗る子どものように
窓にはりついて景色を眺めています。
世界を俯瞰する時間は大切ですね。
今年初となる鹿児島セミナーは
5月7日(土)に鹿児島市内で開催します。
_________
【鹿児島セミナー〜最新情報〜】
https://bit.ly/3JMRkH2
_________
5月14日(土)午後開催
大阪週末クラス
https://shienonekonessblog.wordpress.com/osaka-shumatsu-class-news/
_________
5月21日(土)午後、22日(日)午前開催
東京ワークショップ
https://shienonekonessblog.wordpress.com/tokyo-ws-news/
_________
今回は4ヶ月以上間が空いている
「先師の物語」の続きです。
直接会った際に
「次が出るのを楽しみにしてます!」
と声をかけて下さった方々
ありがとうございます。
お待たせしましたー!
と言うレベルを超えて
時間が経ちすぎているので
ぜひ序章から流し読みしてから
今回も読み進めていただけたらと
思います。
_________
2021年、ある投稿の発見
『先師の物語』〈序章1〉
https://shienonekonessblog.wordpress.com/2021/09/28/chen-style-taichi-story1/
2006年、西安での出会い
『先師の物語』〈序章2〉
https://shienonekonessblog.wordpress.com/2021/10/11/chen-style-taichi-story2/
2008年、先師の弟のお話
『先師の物語』〈第一話〉
https://shienonekonessblog.wordpress.com/2021/10/27/chen-style-taichi-story3/
1928年北京
陳式太極拳を初めて目にした者たちの戸惑い
『先師の物語』〈第二話〉
https://shienonekonessblog.wordpress.com/2021/11/07/chen-style-taichi-story4/
陳発科を本気にさせた?
『先師の物語』〈第三話〉
https://shienonekonessblog.wordpress.com/2021/11/17/chen-style-taichi-story5/
系譜に記されざる伝人
『先師の物語』〈第四話〉
https://shienonekonessblog.wordpress.com/2021/11/30/chen-style-taichi-story6/
先師を敬服していた師兄弟
『先師の物語』〈第五話〉
https://shienonekonessblog.wordpress.com/2021/12/09/chen-style-taichi-story7/
陳発科による毎朝のマンツーマン指導
『先師の物語』〈第六話〉
https://shienonekonessblog.wordpress.com/2021/12/19/chen-style-taichi-story8/
__________________
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
シリーズ第9段
『先師の物語』〜第七話〜
「西安への移住とその後」
__________________
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
例の投稿には、前話の続きとして
陳発科の武徳や誰にも分け隔てなく
包み隠さず教えた彼の人柄、指導方法
などについて語られていた。
北京で投稿の筆者から取材を受けていた
楊益臣先師の弟、楊徳厚氏は
さらに話を続けた。
「兄たちのうち数人は陳発科から学んだ
ことはあったが、毎日家まで通って
しっかり学んだのは2番目の兄(楊益臣先師)
だけだった。
早い時期に学び始めた弟子の中で
最も熱心に学んでいた。
兄は陳発科と性格が似ており
陳発科も彼のことを気に入っていた。
・・・
七七事変(盧溝橋事件)で
二十九軍が日本軍と激戦となった時
多くの重要な部門が緊急移転した。
2番目の兄(先師)、3番目の兄、
3番目の姉の夫は家族を北京に残して
西安へ移動することとなった。
私はまだ高校を卒業したばかりで
北京に残って家の手伝いをしていた。
当時兄たちと西安に行った者たちはみな
陳発科を通して会館で知り合った商人たちで
稼いだお金を北京の家族のめに
持ち帰っており、陳発科老師との間でずっと
手紙のやりとりをしていた。
兄は頻繁に陳老師のところへ伺うように
私に言った。
当時、電報局の最初に学び始めた者たちは
みんな北京を離れることになった。
陳発科は所属する機関もなく
北京に残って指導で生計を立てていたので
一時期生活は困窮した。
1940年代に陳発科はかつて兄に手紙で
西安へ行って指導で家族を養いたいと
言っていた。
しかし
河南省陳家溝から難を逃れて西安に来て
太極拳を教えている人はたくさんいて
しかも西安で指導して得られる収入は
北京のそれには及ばないと返信し
結局陳発科は西安に来なかった。
兄は1937年に西安へ行った後
西安韋曲電報局にいた時
数人に教えていた。
その中の一人「鉄佛」と呼ばれる和尚が
傑出していた。
戦後、西安電報局は城壁内に移転し
兄は蓮湖公園で指導した。

私の知るところでは
陳照旭(※)が戦後の間もない頃に
西安へ兄に会いに行き、家に泊まったという。
私は大学を出て働き始め、様々な理由で
あまりよく練習しなくなり、兄には
遠く及ばなくなってしまった。
・・・
文化大革命後の1972年
私は河南五・七幹部学校から北京に戻り
用事のない時は雷慕尼(※)と
月壇(北京の公園)へ行き一緒に練習した。
その後、私と雷慕尼も
現在の架式に動作を改めた。
私の知っていることはおおよそ
こんなところだ。
その他の情況については西安に戻って
からでも知ることができるだろう。」
2008年頃に北京でなされた取材の内容は
ここまでとなっていた。
私が昨年(2021年)この投稿を
初めて見つけて一気に目を通した時
先師の弟ご自身も兄とともに学んだ套路を
「現在の架式に動作を改めた」
という最後のくだりを読んで
その時代に思いを馳せながらちょっと
切ない気持ちになったのを思い出す。
もちろん
師である陳発科と直接会える環境にあれば
師がその時に伝えている動作に改めて
いくのは当然のこと。
ただこうした一言からも
投稿と出会う前にはボヤッとしていた
よく目にする陳式太極拳と私が西安で
学んだそれとでは架式に違いがある理由や
その背景が見えてくる。
ここでは戦後から文革まで話が飛んでいるが
楊益臣先師はその間の1959年に
亡くなっている。
_________
2021年9月に中国のサイトで
10年以上前に書かれたとある投稿を
見つけたことをきっかけにして
私が西安留学中に学んだ
陳式太極拳の架式がほぼ他団体で
見られないカタチである理由や
伝わった系譜、時代背景などに
ここまで思いを巡らせてきた。
少しずつ書き足して
半年以上が経過した今
「一緒にこの系譜の陳式太極拳を
学んでいる仲間がこの套路に誇りを
持って取り組めるようになる」
という当初の目的はある程度
果たせたのではないかと思っている。
終盤にさしかかった物語、次回は
西安で楊益臣先師から学んだ弟子たち
について触れたいと思う。
〜つづく〜
_________
※陳照旭…(第六話参照)陳発科の息子。
陳式太極拳第18世伝人。
1960年、反右派闘争の際、収容施設を
脱出しようとして射殺される。
陳照丕は従兄。陳照奎は異母弟。
陳小旺は息子。
※雷慕尼
湖北省武昌の人、1911年生まれ、1989年享年75歳。北京市の武術協会顧問、陳式太極拳研究会副会長を務めた。
1928年北京に渡り「北京国術館」に入学し、太極拳をはじめさまざまな武術を習った。このとき紹介で陳発科と知り合い、陳式太極拳を習いはじめ、1932年に陳発科の正式な弟子となった。
____________
【お知らせ】
【鹿児島セミナー〜最新情報〜】
https://bit.ly/3JMRkH2
【大阪週末クラス最新情報】
https://shienonekonessblog.wordpress.com/osaka-shumatsu-class-news/
【東京ワークショップ最新情報】
https://shienonekonessblog.wordpress.com/tokyo-ws-news/
_________